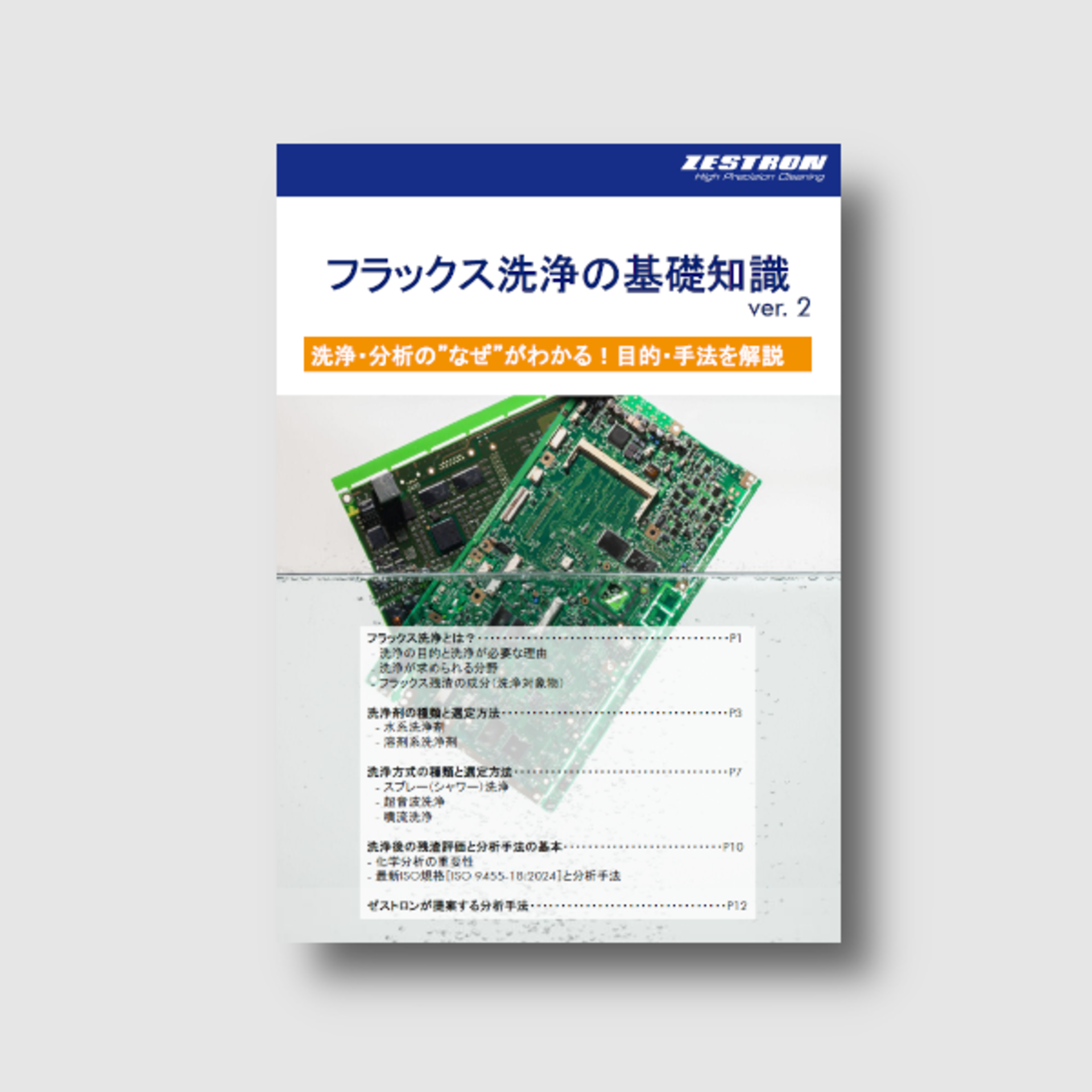フラックスとは?役割や種類、最新トレンドなどを解説
フラックスとは、電子実装やはんだ付け工程で不可欠な補助剤であり、金属表面の酸化膜を除去してはんだの濡れ性を高め、強固な接合を実現する役割を持つ材料です。
本ページでは、フラックスとは何かをわかりやすく解説し、その機能・種類・選び方や最新トレンドまで詳しくご紹介します。信頼性の高い接合品質を実現するための基礎知識として、フラックスの特性と活用ポイントを理解しましょう。
目次
1. フラックスの役割
1.1 母材・部品の金属表面の酸化膜を還元除去する
1.2 接合部の保護
2. フラックスの種類
2.1 フラックスの系統
2.2 工法ごとのフラックスの相違
2.2.1 はんだペースト
2.2.2 ポストフラックスとプリフラックス
2.2.3 はんだボール
2.2.4 糸はんだ
3. フラックス組成の近年のトレンド
3.1 ハロゲンフリー/有機酸系活性剤のフラックスが主流
3.2 接合強度を担保するため、含有する活性剤量は増加傾向
3.4 フラックスレスの技術
3.5 機能性・対候性物質の添加
4. フラックス洗浄事例
4.1 洗浄評価
4.2 まとめ
5. ゼストロンのサポート
6. 関連ページ・資料
公開日:、最終更新日:
フラックスの役割
最適なはんだ付けを可能にするために、フラックスを塗布します。具体的に、フラックスの役割は主に2つあります。
1 | 母材・部品の金属表面の酸化膜を還元除去する
接合させる金属表面に、異物や酸化膜があるとはんだ付けが上手くできません。
そのためフラックスにより表面酸化膜を除去し、はんだ濡れを促す必要があります。
金属表面の酸化膜をフラックスにより除去


表面張力を小さくし、濡れ広がりを促す

※はんだ付けとは?
「はんだ」と呼ばれる合金を熱によって溶かして固めることにより、電気的に接合する技術のことです。部品と母材の間で、金属結合を形成することで、電気伝導性・機械強度・放熱性を確保することができます。
2 | 接合部の保護
フラックスははんだ付け後において、接合部の保護をする役割があります。

フラックスははんだ付け後、還元や熱分解により活性が大きく下がり、残渣の絶縁性が上がることで、はんだ付け部を保護することが可能です。
ただし、残渣にゴミや水分が吸着し、溶剤が残留することで絶縁性の低下や腐食の要因となるため、接合時の環境(空気中の清浄度・温湿度など)にも配慮が必要です。
フラックスの種類
フラックスの種類は大きく分けると無洗浄タイプと洗浄タイプに分かれ、活性剤の活性力によって大別されています。無洗浄タイプのフラックスは、フラックス残渣が安定化するように設計されており、基本的に洗浄不要なフラックスです。
対して洗浄タイプのフラックスは、高活性な物質を多く含んでいるため、洗浄は必須となります。
| フラックス | 無洗浄タイプ | 洗浄タイプ | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 低活性 | 中活性 | 高活性 |
| 腐食性 | 腐食なし | 若干の腐食あり | 腐食大 |
| 絶縁抵抗性 |
フラックス残渣を洗浄せずに1.0×10⁸Ω以上 |
残渣洗浄して1.0×10⁸Ω以上 |
残渣洗浄して1.0×10⁸Ω以上 |
フラックスの系統
ロジン系(RO)、レジン系(RE)、有機系(OR)、無機系(IN)の4種類があり、現在の日本においてエレクトロニクス実装におけるはんだ付けに用いられるのは、ロジン系フラックスが主流となっています。
しかし、SDGsなどの環境意識の高まりから水溶性フラックスへの転換を模索する動きも見られています。
フラックスとはんだ粉を主成分として溶剤やチキソ剤などを添加し混合されたものが「はんだペースト」(もしくはクリームはんだ、ソルダーペースト)です。
はんだペーストは、印刷法orディスペンス法のいずれかの方法で供給され、基板に塗布された後、リフロー炉を通りはんだ付けが完了します。
酸化の影響を抑制するためにリフローによる接合は窒素雰囲気下で行われ、最新の技術としてはフラックスの還元作用の役割も担うギ酸リフローによる接合が取り入れられているケースも増加しています。

▼リフロー炉接合のイメージ

金属粒子はリフロー時の熱で溶解して合金化し、フラックス成分が残渣として形成される。
印刷法・ディスペンス法の両者ともにフラックスが他成分と混合されている点は同様ですが、ディスペンス法では塗布後のはんだペーストの形状保持性や押し出し性にも留意しなくてはならず、より繊細なハンドリング性が求められる傾向にあり、樹脂成分やフラックス量が多い傾向にあります。
よって同一型番のはんだペーストであってもディスペンスタイプの仕様の方が、洗浄は難化する傾向にあると言えます。

印刷法:基板上にメタルマスクを配置して、スキージングして転写する。
ディスペンス法(塗付法):基板に対し、クリームはんだを直接塗布する。
※ポッドは印刷法、シリンジはディスペンス法に用いられる
2 | ポストフラックスとプリフラックス
一般的にフラックスと言われているものは、ポストフラックスのことを指す事が多く、プリント基板上の金属表面保護のために使用されるプリフラックス(OSP)と区別されています。
ポストフラックスは主にフローソルダリング工法で使用され、フラクサーではんだ付けする前の基板に吹き付けられた後、はんだ槽にてはんだ付けされます。
▼フロー接合のイメージ

★フラックスは広範囲に分布する事となり、リフローと比較して相対量も多い
3 | はんだボール
薄層化を目的としてコネクタの使用を避け、直接マザー基板等へ接続する手法として、はんだボールにて行う実装も近年増加しています。
メタルマスクとスキージを使用し、フラックスを母材にあらかじめ印刷し、その後フラックスが印刷された位置にはんだボールを置き、リフロー炉にてはんだ付けを行います。
▼はんだボール実装のイメージ

はんだゴテを使って電子部品を実装する際に使用されます。
外面は細い金属の線材ですが、中にフラックスが固形物として含まれており、ヤニと呼称されています。
はんだゴテで糸はんだを随時溶融させ実装をしていきます。

基板の大きさや半田の種類で設備の制限・調整を受けること無く、維持コストも軽微、玄人の作業者の方は機械では難しいような作業内容もこなせるため、未だに愛用されているケースが多いです。
部分修正方法としてもメジャーです。基本的に大気中でのはんだ接合となるので、フラックス残渣の洗浄は窒素雰囲気下で接合した場合と比較し難化します。
フラックス組成の近年のトレンド
1 | ハロゲンフリー/有機酸系活性剤のフラックスが主流
過去、電子材料は難燃剤としてハロゲン化合物が使用されてきましたが、ハロゲン化合物を含む材料は不完全燃焼によりダイオキシン類が生じる懸念があり、ハロゲン化合物の削減が求められています。フラックス中の活性剤も例外ではなく、徐々に有機酸系活性剤にシフトし現在に至ります。
[規定]
電子業界団体であるIPCは、フラックスの最新規格J-STD-004Bにて全ハライドを測定対象とし、低ハロゲンの定義を Cl + Br < 1,000ppm としています。
JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)が規定するハロゲンフリーは、F、Cl、Br、I の含有量がそれぞれ1000ppm以下、となっています。各ハロゲンを700ppm以下と設定するような動きも見られます。
高密度実装・微細接合の需要が増加するなかで接合強度を担保するため、フラックス中の活性剤含有量は増加傾向にあります。
上記に示すように現在主流となっている有機酸はハロゲンと比較すると作用は限定的であり、ハロゲン系活性剤と同等の作用を得るためには多くの有機酸を使用しなくてはなりません。
その副作用の一例として金属塩形成の課題が挙げられます。時としてマイグレーションの発生やアンダーフィル充填時の阻害要因となる金属塩は除去する事が求められますが、従来の洗浄方法では対応が難しいケースも少なくありません。
金属塩形成で最も課題となりやすい金属はPbフリーはんだの主成分となる「Sn」ですが、複合化合金の場合は「Bi」といったレアメタル系の金属塩も発生するケースもみられ、洗浄時には注視する必要があります。
▼チップ抵抗下部のフラックス残渣

SEM-EDXの分析画像(Sn塩の分布)
ご協力:日本電子株式会社様
3 | Pbフリー品におけるハロゲン仕様のフラックス(高信頼性分野)
上記で示したように現在の日本では多くの製品に対してハロゲンフリー技術が浸透していますが、一部の製品群では根強くハロゲン化合物を活性剤として使用したフラックスを継続利用しているケースが見られます。
高信頼性デバイスの中でも特殊センサーや超高精度の微細接合が必要とされる分野では、濡れ性の確保や接合性の観点からハロゲン系活性剤が用いられています。
ハロゲン系活性剤の作用は強力ですが、洗浄が必要となった場合は確実な除去が求められます。
独自の検証結果(弘輝様との共同研究)からハロゲン系活性剤は有機酸系よりも除去しやすい傾向が確認されておりますが、残留してしまった場合はイオンコンタミネーションとしての作用も強いため注意が必要です。
センサー系の部材は接合面が低スタンドオフ/複雑な接合面となる事が多く、洗浄時の難度は高いと言えます。
▼ハロゲン化合物

強力な活性作用
→イオンコンタミネーションとしても影響大

ICチップの接合面はバンプ構造以外にも複雑な形状となるケースが増加
4 | フラックスレスの技術
例としてギ酸リフローに挙げられるような低残渣仕様のはんだ接合技術が、パワーデバイス分野を中心に活況となっております。ボイドの低減効果も大きく非常に有用な接合手法となります。
しかし、下図に示すようにパワーデバイスにおけるスリーブ内の洗浄性が問われるケース、モールド樹脂の接合強度アップが求められる場合は表面状態を整えるべく洗浄を行う場合が少なからずあります。
理由としては環境由来のイオンコンタミネーションのケアや銅表面の酸化物除去などが挙げられます。
▼スリーブ内部の洗浄

▼銅酸化物の除去

また、はんだによる接合では十分な熱耐性を得る事が難しい分野ではシンター接合の技術が採用されています。
基本的にシンターは無洗浄での設計がなされていますが、同様の理由から洗浄が必要となるケースが見受けられます。
▼シンター接合における有機物残渣

5 | 機能性・対候性物質の添加
市場の要望に対してはんだ接合は多岐に渡る高性能化が求められています。
そこで、接合強度のアップ・フラックス飛散防止・熱追従性・経時安定性など様々な特性を得るために多種多様な物質がフラックスには添加され高機能化を果たしています。
ですが、高機能性を付与するために添加されている物質は化学的には安定化度合いが高く、有機溶剤や酸・アルカリに耐性がある物質が多いです。
洗浄を行おうとした場合はこれらの安定性の高い物質への除去対応力が求められます。

機能性物質の多くは対候性に優れるため、洗浄時には強力な作用が必要
【フラックス洗浄事例】
難溶性物質含有のフラックス残渣×低スタンドオフ部洗浄
フラックス組成の近年のトレンドで解説した背景により、以前と比べ洗浄の難易度が上がっています。
今回は、機能性・対候性物質の添加で紹介した有機溶剤や酸・アルカリに耐性がある物質(難溶性物質)を含有しているフラックス残渣と低スタンドオフという組み合わせで構成されたサンプル基板の洗浄を行った評価をご紹介します。


洗浄後
| ハロゲン系溶剤 | ゼストロン洗浄剤(VIGON® PE 305N) |
 |
 |
|
フラックス残渣を部分的に溶解した痕跡が伺える。 |
洗浄液が中心まで入り込めており、洗浄できている。 |
|
洗浄方法:超音波 |
洗浄方法:スプレー |
ハロゲン系溶剤での洗浄と比較し、VIGON® PE 305Nにおいては短時間で難溶性物質が含まれるフラックス残渣であっても、優れた低スタンドオフ部の洗浄性を発揮しました。
この結果が得られたのは、VIGON® PE 305Nの剥離を主とした洗浄技術でフラックスを流動化させ、スプレー方式により効率的にスタンドオフ内部の置換性を確保できたためです。

昨今のフラックス洗浄においては、洗浄剤だけでなく洗浄方式との兼ね合いも重要になります。現代のフラックス残渣は高機能化に伴い「複合化」した成分で構成されているため、ある特定の物質の溶解性に優れるだけでは洗浄剤としての能力も限定的となってしまいがちです。
洗浄方式の種類と選定方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
フラックス洗浄方式の種類と選定方法
フラックス洗浄でお困りごとやトラブルがある場合やこれからフラックス洗浄を始めたい場合は、ゼストロンにぜひご相談ください。
フラックス洗浄事例で解説した通り、洗浄においては洗浄剤だけでなく洗浄方式も重要です。
ゼストロンのテクニカルセンターには、インライン・バッチ式のスプレーや噴流、超音波装置をご用意しておりますので、弊社エンジニアよりお客様のワークに合った洗浄剤・洗浄方式を見つけるサポートをいたします。

また、洗浄テストと並行しながら分析センターにて清浄度を化学的観点から分析し、テスト終了後には、推奨プロセスなどの詳細を記載したテクニカルレポートを提出させて頂きます。
洗浄テストをご希望の方は、ぜひご依頼ください。
洗浄から清浄度分析までワンストップで
洗浄を検討するにあたって、洗浄剤だけでは完結しません。
弊社は洗浄剤メーカーではありますが、ワークに適した洗浄方式を選択するこ と、そして洗浄後の分析も重要と考えています。
そのため、洗浄剤のご提案だけでなく、洗浄方式の選定、清浄度分析もサポー トさせていただきます。